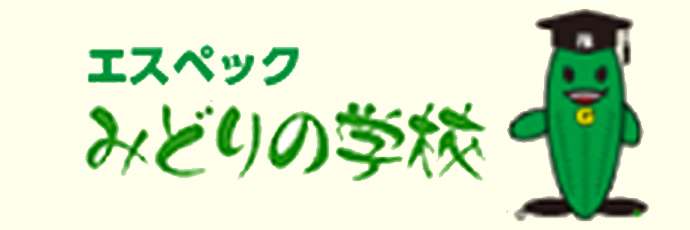TCFD提言に基づく
気候関連財務情報開示
当社は、気候変動がもたらすリスクおよび機会の財務的影響を把握し開示することを目的とした「気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)※」の提言への賛同を表明し、気候変動に関する情報の適切かつ積極的な開示に努めています。
※Task Force on Climate-related Financial Disclosures.
金融安定理事会(FSB)により2015年に設立

ガバナンス
気候関連リスクと機会にかかわるガバナンス
エスペックグループの主力事業である環境試験事業(販売・サービス・受託試験)は、使用時のエネルギー消費に起因するCO2排出量が大きく、冷凍機に冷媒として使用されているフロンは気候変動に影響を与えます。当社事業が気候変動に与える影響は大きいと認識しています。また、グループ会社であるエスペックミック株式会社が展開する環境保全事業等では、気候変動により直接的にも間接的にもさまざまな影響を受けます。気候変動問題は、当社の中長期的な事業リスク・機会に大きな影響を与えると考えています。
当社は「持続可能な社会の実現のために事業で貢献する環境経営」を目指しており、この考えに基づいて環境保全上のマテリアリティ(重要課題)を特定しています。まず、事業活動のどの段階でどれくらいの環境負荷が発生しているかを「環境影響評価」で評価・把握し、課題を抽出しています。さらに、外部・内部の課題の分析、主たる事業拠点が立地する地域(行政)・地域住民、顧客、供給者(取引先)、従業員、投資家などのステークホルダーからのニーズと期待を整理しています。その結果抽出された課題と、中期経営計画との整合を図り、環境保全上の重要課題を環境中期計画に落とし込んでいます。
第8次環境中期計画では、地球温暖化対策と生物多様性を経営上の重要な課題として掲げており、低炭素技術開発分野への製品・サービスの提供や、環境配慮型製品の開発・提供、事業活動におけるCO2排出量の削減などに取り組み、環境経営をさらに推進してまいります。
当社では、1996年度より代表取締役 執行役員社長を委員長とする全社環境管理委員会において、四半期ごとに当社グループの環境課題に対する実行計画の策定と進捗モニタリングを行っています。代表取締役 執行役員社長は、「執行役員会」の議長を担うと同時に、諮問委員会である「全社環境管理委員会」の委員長も担っており、環境課題に係る経営判断の最終責任を負っています。「全社環境管理委員会」では全社共通の目標管理、各種案件の審議などを行っています。ここでの決定が、それぞれの会社、事業所、事業部に展開され、活動が推進されます。
取締役会は、四半期ごとに「全社環境管理委員会」で協議・決議された内容の報告を受けることで、当社グループの環境課題への対応方針および実行計画等についての議論・監督を行っています。
戦略
事業・戦略・財務に対する気候関連リスクと機会の影響
環境試験器の需要は、カーボンニュートラル社会に向けた環境配慮技術の開発が進むことにより、今後増加すると予測しています。また、キガリ規制など冷媒を使用する空調機器や冷凍機搭載機器の需要の増加によって、各国政府は空調に伴うエネルギー規制や、温室効果の高い冷媒に対する規制を強化する可能性があります。過度な規制強化は当社にとってリスクとなり得ます。一方、適正な規制は、当社が強みとする環境性能に優れた製品・サービスの普及拡大を後押しし、事業拡大の機会となり得ます。環境配慮技術を世界に先駆けて開発する欧州やASEANなどを中心に当社の環境配慮製品・サービスを普及させていくことが、世界の温室効果ガス排出抑制に向けた有効な施策であり、かつ、当社事業の成長につながると考え、事業戦略に反映しています。
当社は、1996年から環境中期計画を設定し、これまでもCO2排出量削減に取り組んできました。昨今の社会的要請の高まりを受け、2022年4月に「第8次環境中期計画」を定め、2030年のCO2排出量(SCOPE1+2)削減目標を60%減(2019年度比)と設定しました。
その実現のため、国連気候変動に関する政府間パネル(IPCC)が第6次報告書で公表したSSPならびに第5次報告書で公表したRCPシナリオなどを考慮し、下記のとおり事業活動に与える気候関連のリスク(物理リスクおよび移行リスク)と機会を抽出し、対応策の有効性およびレジリエンス(強靭性)を検証いたしました。
第8次環境中期計画では、日本政府がめざす2050年カーボンニュートラルに賛同し、省エネ製品や低GWP冷媒採用製品の拡販、グローバル事業所でのさらなる省エネ活動と再生可能エネルギー100%での受託試験サービスの提供などに取り組んでまいります。
<シナリオ分析の詳細>
使用シナリオ
- 4℃シナリオ:IPCC AR6 SSP3:共通社会経済経路(Shared Socio-economic Pathways )および AR5 RCP8.5代表濃度経路シナリオ(Representative Concentration Pathways)
- 1.5もしくは2℃シナリオ:IPCC AR6 SSP1共通社会経済経路(Shared Socio-economic Pathways)およびIPCC AR5 RCP2.6代表濃度経路シナリオ(Representative Concentration Pathways)
気候関連リスク・機会に対する事業インパクト(財務影響と事業リスク)評価と当社の対応
左右にスクロールしてご覧ください。
影響時期:短期10年以内、中期10年~30年、長期30年超
財務影響度:★1億円以内、★★1億円~10億円、★★★10億円超
リスク管理
当社では、リスク管理委員会と全社環境管理委員会および環境マネジメントシステム(ISO14001)で上記に記載した気候関連のリスクを管理しています。
リスク管理のプロセスとしては、リスク管理委員会と全社環境管理委員会および環境マネジメントシステム(ISO14001)にてリスクの識別・評価を行い、発生頻度やインパクトから優先順位付けした上で、回避・軽減・移転・保有などの対策を決定し、進捗管理を行います。重要リスクについては定期的に取締役会に報告され、取締役会による監督体制の下、当社グループの戦略に反映し、対応しています。
指標と目標
気候関連リスクと機会を評価・管理するための指標と目標
(a)気候関連リスク・機会の管理に用いる指標
当社は、気候関連リスク・機会を管理するための指標として、SCOPE 1・2およびSCOPE 3温室効果ガス排出量の2つの指標を定めています。
(b)温室効果ガス排出量(SCOPE 1・2・3)
当社は、2019年度から、グループ全体の温室効果ガス排出量の算定に取り組んでいます。当社グループの2022年度SCOPE 1・2温室効果ガス排出量は、7,293t-CO2e(対2019年度48.2%減)でした。また、2022年度SCOPE 3温室効果ガス排出量は、約1,098,905t-CO2e(対2019年度比35.1%増加)でした。
当社グループは、2019年度から、温室効果ガス排出量の第三者保証を取得しており、2022年度の温室効果ガス排出量についても、第三者保証を取得済です。
(c)気候関連リスク・機会の管理に用いる目標および実績
当社では、2030年までの温室効果ガス排出量削減目標を4年ごとに設定する「環境中期計画」に展開し、環境目的・目標に落とし込みを行い、地球温暖化対策を含む環境活動の進捗を管理してまいります。
SCOPE 1・2:グループ全体の事業活動に起因する温室効果ガス排出量
2030年60%削減(2019年度比)
→第8次環境中期計画 2025年55%削減(2019年度比)
SCOPE 3:販売した製品の使用(カテゴリ11)+販売した製品の廃棄(カテゴリ12)の温室効果ガス排出量
2030年30%削減(2019年度比)
→第8次環境中期計画 2025年排出量 10%削減(2019年度比)