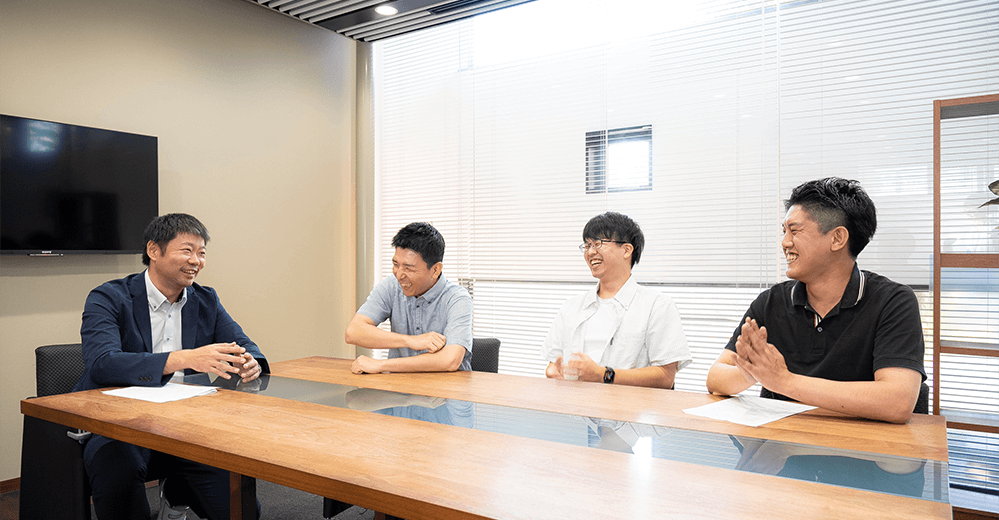技術系座談会
取引先様とのコラボレーション商品開発を行うために発足した“社外コラボレーションプロジェクト”。約1年かけて取り組んだプロジェクトの軌跡を当初のプロジェクトメンバーが語る。
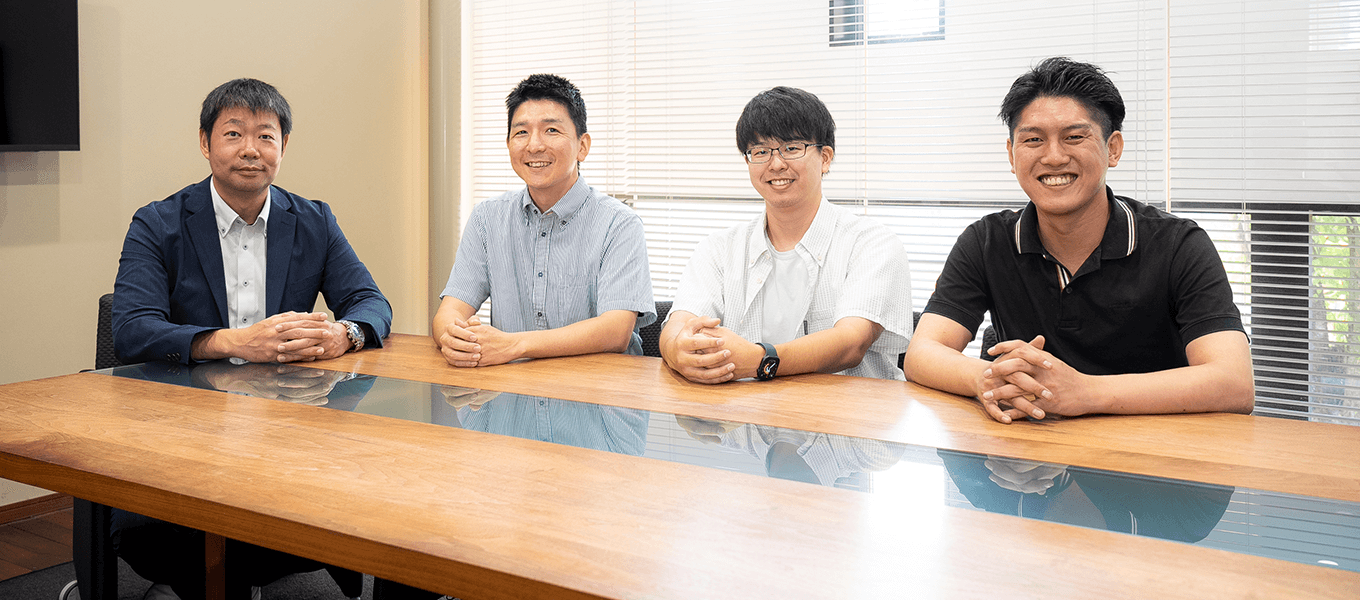
メンバー紹介
-
 N.K
N.K環境テスト機器本部 本部長
2003年入社 大学院 生産科学研究科卒本プロジェクトの生みの親。
メンバーのアサインやプロジェクトの環境づくりに努める。 -
 K.K
K.K環境テスト機器本部
付加仕様設計グループ
2021年入社 大学院 システム工学研究科卒(プロジェクトリーダー)
プロジェクトメンバー最年少ながらリーダーに抜擢。進行やお客様との折衝調整・設計を行う。 -
 J.H
J.H環境テスト機器本部
付加仕様設計グループ
2005年入社 理工学部 精密機械工学科卒プロジェクトメンバー最年長の設計職として、リーダーのサポートやチームの黒子に徹する。
-
 M.S
M.S環境テスト機器本部
マーケティンググループ
2015年入社 政策学部 政策学科卒マーケティングGにて市場調査やニーズのヒアリングを行い、商品のコンセプトを設計する。
プロジェクト発足の背景
このプロジェクトの始まりは、本部長のN.Kさんが取引先様との会話の中で共同開発の話が出たことがきっかけです。取引先様が手掛ける計測器とエスペックの環境試験器を組み合わせ、その相乗効果を活かして、より優れたソリューションを提供することを目的に発足しました。
そうですね。企画の原点は、エスペックの環境試験器と取引先様の新製品を組み合わせて、面白いものができないかという発想でした。
お客様とのコラボレーションは初めてだったので、半分不安、半分楽しみな気持ちでした。
取引先様との話がまとまったところで、プロジェクトメンバーを公募することになりましたが、みんなはどのような経緯でこのプロジェクトに参加したのですか?
私は単純に「面白そうだな」と思ったのが一番の理由ですね。普段の業務ではやらないことなので、技術者として挑戦したいという気持ちが強かったです。
私も同じく、普段は設計業務に携わっていて、他社と話をする機会やプロジェクトを進める経験がなかったので、成長のチャンスだと思って手を挙げました。
私の場合は所属していたマーケティングGでは、ただ製品を提案する商品提案ではなく、お客様が実際にされる試験方法、環境を想定した試験提案をする事を目標として掲げていました。そうした中、このプロジェクトが発足されることになったときに、自社製品だけでは出来ない試験提案を出来る可能性があるプロジェクトだと思い、参加しました。私の場合、所属していたマーケティンググループでは、ただ製品を提案するだけの商品提案ではなく、お客様が実際に行う試験方法や環境を想定した試験提案を行うことを目標としていました。そうした中、このプロジェクトが発足した際、自社製品だけでは実現できない試験提案ができると考え、参加しました。あと、プロジェクトに参加しているメンバーを見て「このメンバーなら楽しくやれそうだ」と思ったのも理由の一つです。
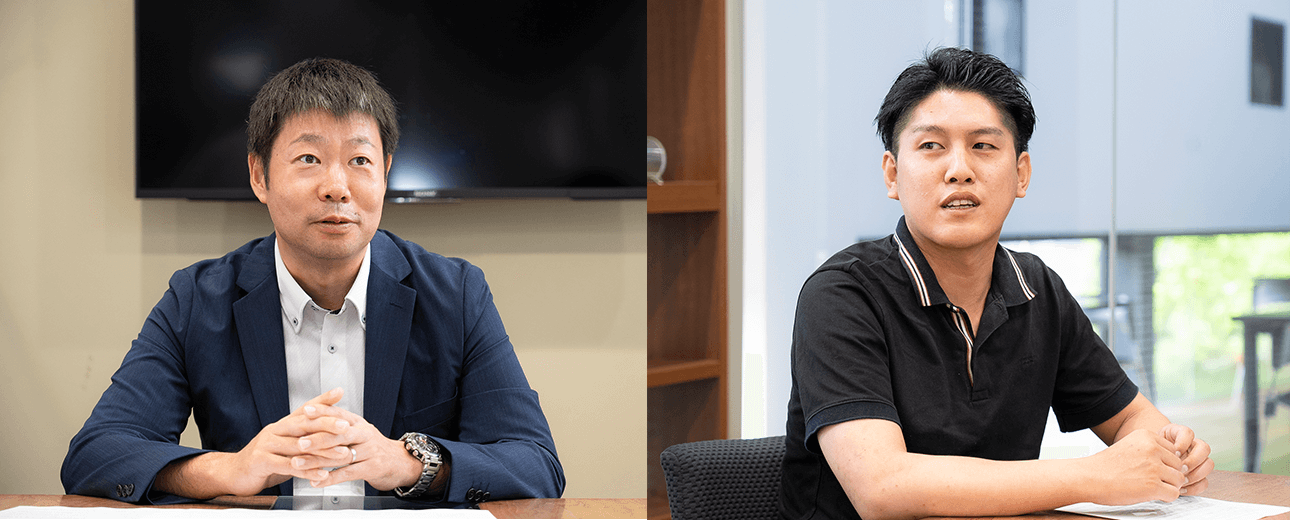
プロジェクトにおける
それぞれの役割と苦悩
プロジェクトが始まった後、みんなはどのような役割を担いましたか?
私はプロジェクトリーダーを務めました。案件を進める上での調整やお客様との折衝業務、さらに設計者として構造的な部分にも関わりました。経験が浅かったのですが、周りから「せっかくだからリーダーやってみよう」と背中を押してもらい、リーダー役の挑戦を決断しました。
私は「このプロジェクトをどう盛り上げるか」が自分のミッションでした。チーム内で最も経験があったので、問題が発生した際には解決策を出すことを常に意識していましたね。
私の役割は大きく2つ。1つは社内外への広報活動で、社内では営業への売り方をレクチャーし、社外では展示会や販促活動で「社外コラボレーションプロジェクト」の認知を広めました。もう1つは、その活動を通じて得たフィードバックを設計者に伝え、製品の改善に活かすことでした。
苦労した点や挫折はありましたか?
お客様のニーズに応じて製品を作る難しさですね。技術的な難しさに加え、仮説が正しいのかどうかも不安でした。例えば、当初は大きなモノを試験する仮説を立てたのですが、実際はもっと小さいモノにニーズがあったりと、見えないニーズに向き合うことが大変でした。
計画の見積もりが甘く、日程が厳しくなったことに苦労しましたが、最終的にはJ.Hさんに相談してレールを敷いてもらうことで何とか事なきを得ました。また、お客様との折衝では、普段経験することがないため緊張してしまい、意思疎通がうまくいかないこともありました。
K.Kさんは最年少だから、僕たちに言いにくいこともあったんじゃないかな?
そんなことは全くなくて、J.Hさんをはじめ、皆さんが普段から言いやすい雰囲気を作ってくださったので、伝えたいことはしっかり伝えられましたよ。

私は「売りたい!」という思いが強かったのですが、なかなか結果に結びつかないことが苦労でしたね。顧客ニーズを読むのは難しいと痛感するとともに、営業の凄さを改めて感じました。
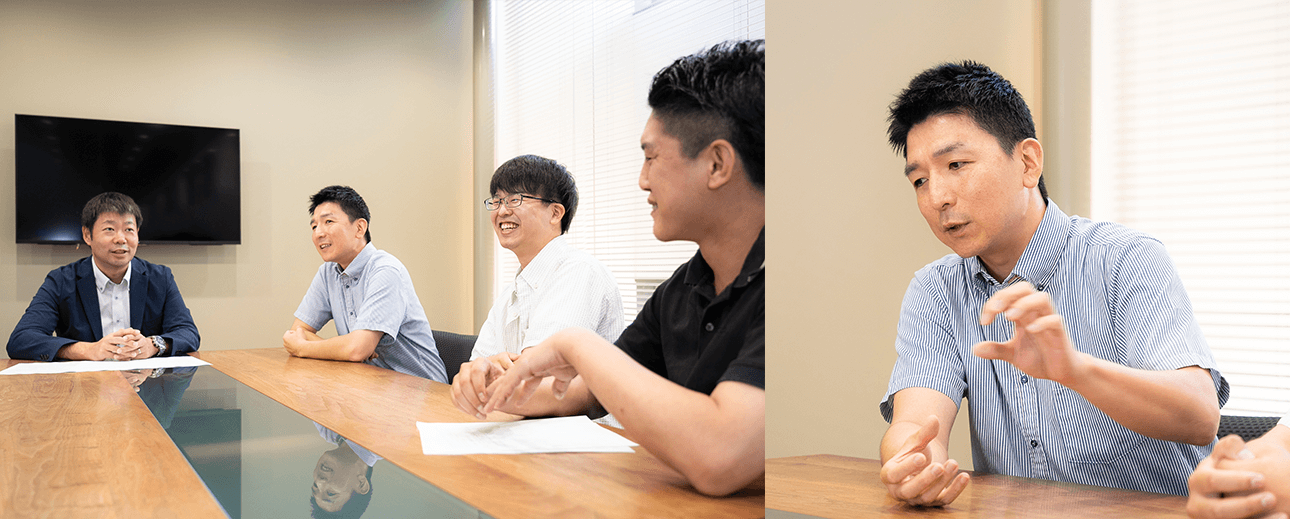
プロジェクトを終えてみて
プロジェクトを終えて、どのように感じていますか。
先ほどの話にも関連しますが、商品を売ることの難しさを痛感しました。今後は、もっと営業の視点に立って製品設計を進めようと思っています。売りやすい設計や、問い合わせにすぐ対応できる体制など、このプロジェクトを通じてたくさん学ぶことができました。
社内チャットを通じて励ましやフィードバックをいただくなど、全社的に注目されたプロジェクトだったと思います。また、リーダーとして進めていく中で、ゴールから逆算したスケジュールの立て方も学び、設計者としてそれを意識していこうと感じました。
リーダーを経験することで、周りの意見を聞きながら進める方法も学べたんじゃないかな?
そうですね。エスペックは若手の挑戦を後押ししてくれる会社で、僕がやりたいことにも本部長のN.Kさんが背中を押してくださったので、挑戦しやすい環境でプロジェクトに取り組めました。このプロジェクト自体が、まさに"挑戦"でしたから。

みんながこの挑戦を楽しんでくれたのが、何よりも嬉しいです。1年間という長いプロジェクトだったけど、何か思い出に残ることはありますか?
このメンバーは本当にチームワークが良かったですね。展示会に行った時も、3人とも違う視点で情報を集めていて、役割や職種に偏りがないバランスの取れたチームだった。それがプロジェクト成功につながったんじゃないかなと思います。
一番印象に残っているのは、最後のお客様との打ち合わせです。すごく盛り上がって、『もっとこういうことをしたい』『次はこんなのを作りましょう』といった話が出ました。第2弾も期待できるんじゃないでしょうか。
きっとあると思うよ。僕としては、途中で大変そうな部分もあったけれど、最終的には※社内のコンテストで事業成長賞をもらえて、会社の成長にもつながるプロジェクトになったことが嬉しいですね。会社に入ると、どこまで新しいことに挑戦していいのか迷うこともあるけれど、エスペックは挑戦する人を応援してくれる風土がある。まずは自分がやりたいことをとことんやってみてほしい。それが技術者としての成長につながると思います。
※社内コンテスト:職場内における慣性と惰性を打破するため、各部署の新しい取り組み事例を社内で共有し、組織活性化に繋げていくことを目的としたコンペティション。優秀な事例は表彰される。